はじめに
「AIで作った音楽だから著作権フリーでしょ?」と思っている方、ちょっと待ってください。実はAI音楽にも、思わぬ落とし穴が存在します。使用方法によっては法的トラブルや収益化の妨げになることも。今回は、知らないと危ない3つの罠を紹介し、安全に活用するためのポイントをお伝えします。
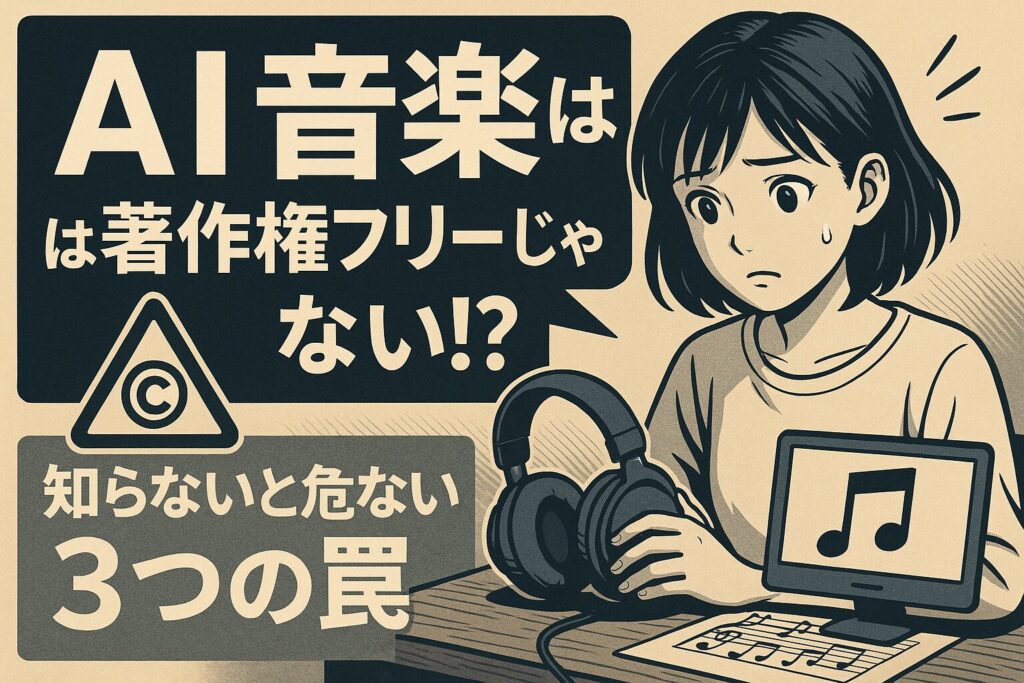
罠①:商用利用がNGなAI作曲ツールがある
無料で使えるAI作曲ツールの中には、「商用利用禁止」と明記されているものもあります。たとえば一部の無料プランでは、YouTubeや販売サイトへの投稿がNGとされています。
対策:ツールごとの利用規約を必ず確認しましょう。商用利用可能なプランにアップグレードするか、最初から明確にOKなサービス(例:Soundraw)を選ぶのが安心です。
罠②:既存音楽に似すぎていると著作権侵害になる可能性
AIは既存の楽曲から学習しているため、意図せず似たメロディや構成を生み出すことがあります。それが著作権侵害と判断される可能性もゼロではありません。
対策:公開前に自動生成された楽曲をチェックし、他作品と酷似していないか確認しましょう。商用展開を考えている場合は、再構成やアレンジを加えるのも有効です。
罠③:「AIが作った=著作権がない」は誤解
一部では「AIが作った音楽には著作権が存在しない」と誤解されていますが、これは国やケースによって異なります。作曲ツールの運営元が著作権を保持しているケースもあり、ユーザーに自由使用が許されていないことも。
対策:AI音楽を使用する際は、著作権の所在(ユーザーか企業か)とライセンス範囲を確認しましょう。
安全にAI音楽を活用するには?
- ✅ ツールの利用規約を読む(商用利用OKか明記されているか)
- ✅ 生成された音源は事前にチェックし、必要に応じて修正・リミックス
- ✅ ストック販売やYouTube利用時には、著作権フリーを証明できる状態にしておく
まとめ
AI音楽は便利で副業にも活用しやすい一方で、著作権にまつわる問題には細心の注意が必要です。知らなかったでは済まされないトラブルを避けるために、ツールの規約確認と音源チェックを徹底しましょう。正しく使えば、AI音楽はあなたの強力な収益源になります。
他の記事
AI作曲ツール5選!無料で始められる音楽副業入門 – AIマネーライフ
主婦でもできるAIライティング副業!家事の合間に文章で稼ぐ – AIマネーライフ
AI音楽は稼げる?人間の作曲との違いと可能性 – AIマネーライフ
1件のフィードバック